予定変更のお知らせ
前回の話の続きとして,すぐにでも放射線の正体やその性質についての話をするつもりであった.できるだろうと思っていた.しかしその話を準備していくうちに,どうしても電子の発見の物語の方を先に知っていた方が良いという考えに傾いていった.それで,予定変更だ.
電子という粒子が存在することを決定づけることになった実験がある.それについてだけ話すのなら簡単に終わらせることもできるのだが,今回は敢えて時代を遡ることにする.その歴史の中には素粒子実験の本質がすでにあり,放射線の正体を知ることになった実験もその積み重ねの中からヒントを得ているのである.素粒子について知る上で無駄な知識にはならないだろう.
真空放電の実験
19 世紀後半,つまり 20 世紀に突入する少し前の物理学では真空放電の研究が流行っていた.空気というのは絶縁体で電気をほとんど流さないのだが,ガラス管の中に電極を封入して電圧をかけ,真空ポンプで中の空気を抜いてゆくと,ある段階から電流が流れやすくなる.しかもガラス管の中が光るのである.これは不思議で面白い!とは言っても数千ボルトは必要なのだが.
このような実験はもっと前からあったのだが,詳しく調べ始めたのはファラデーであり,1836 年にその記録がある.ちょうど電磁気についての系統立った知識を人類が手に入れ始めたころである.1850 年を過ぎた頃から,より希薄な真空を作る技術が発達し始め,真空度や電圧によって様々なパターンの放電があることが分かるようになってきた.これはガラス細工の技術の発達によるところが大きい.
1858 年には,マイナス極側に近いガラスが蛍光を発していることが観察され,やがて様々な実験によってその原因はマイナス極から何か光のようなものが出ているせいだということが突き止められた.それはやがて「陰極線(Cathode-ray)」と名付けられた.陰極線それ自体はあまり良くは見えないのだが,それが蛍光板に当たると,はっきりと分かる光を発する.陰極線の進路の途中に物体を置くと,蛍光板にその影がくっきりと現れるので,陰極線には直進する性質があるということも分かった.その進路は磁石によって曲がることも分かった.
ある者はそれはエネルギーの波,あるいは電磁波だという説を立て,ある者は粒子だと主張した.
ガラス管に入れる気体の種類を変えてやると,その物質によっては色鮮やかな放電の光を放つ.ネオンサインの光もその一種だ.その光の成分をプリズムで分解して観察すると,それぞれの物質に特有のパターンが見られるのである.そのようなパターンを研究する分野は「分光学」と呼ばれていた.これは後に原子の構造を解き明かすのに非常に役立つことになった.この分光学による様々な観察結果は量子力学が導く理論的な結果とよく比較されて,理論を正しい方向へと導いていく助けになったのである.
真空放電とは何か
ところでガラス管の中の空気を抜いて行くとなぜ電気が流れやすくなるのだろうか.絶縁体である空気がなくなれば確かに電気の進路を邪魔するものはなくなるわけだが,真空には電気を伝えるものさえ存在していないではないか.
これについては現在の知識を使って簡単に説明してしまうことにしよう.金属の表面からはわずかな電子が熱の振動エネルギーに弾かれて飛び出したり戻ってきたりしている.これを「熱電子」と呼ぶ.高い電圧を掛けると,ガラス管の中に電場が生じるので,熱電子はこれによって加速され,金属表面を離れてプラス極へと向かう.ところが気体分子が一杯あるうちは,十分に加速する前に分子に衝突してしまって,簡単に運動エネルギーを失うわけだ.
では気体分子が少しもなければ進路を遮るものがないので,電子は無事にプラス極へと到達できるということだろうか.その通りである.しかし熱電子というのはあまりに数が少なくて,これだけでは電流とは呼べないくらいである.それは何アンペアくらいかと聞かれても答えるのは難しい.金属表面が熱されているほど熱電子の数は増えるし,表面積が大きいほど数は多いだろう.それに金属の種類によってもその数は違っている.常温ではμアンペアのレベルにも届かないくらいではなかろうか.
そのあたりの値が気になる人はリチャードソン・ダッシュマンの式というものを調べると良い.熱電子による電流密度は
という形で表されるそうで,たとえ小さな仕事関数
を持つような金属を選んで 300 ℃ くらいに熱したとしても,1
もの広さの全体を合計してようやくμアンペアくらいになるレベルである.ただしこの式は温度の変化に敏感なので,さらに数百度上げるといきなり増える事も分かる.このあたりは自分でグラフをいじってみないことには実感できないかも知れない.ちなみに真空管では熱電子を積極的に利用するために,真っ赤になるくらいのヒーターでマイナス極側の金属をあぶるのである.
とにかく常温では熱電子は非常に少ないのである.それでも電気放電という大量の電気が流れる現象が起こせるのだから,熱電子以外に何か別の理由があるはずだ.答えはこうである.熱電子が十分な距離を分子にぶつからずに加速することができれば,十分に蓄えた勢いで分子に衝突して,分子の中の電子を弾き出すことができる.その弾き出された電子さえもが電場によって加速して,さらに他の分子に勢い良くぶつかり電子を弾き出す.こんな具合にして次々に電子の大量生産が行われるわけだ.だから気体の分子は多すぎても邪魔になるし,少なすぎても電子の大量生産は行われないことになる.
こうしてガラス管の中のプラス極には最終的に大量の電子が到達するだろうことは説明できた.しかしこんなことがいつまでも続けられるものだろうか.電子を奪われた気体分子は,電子の体当たりを受ける度に無限に幾つでも電子を吐き出せるというわけではない.となれば,ガラス管の中の電子の源はすぐに枯渇してしまうはずだ.
それに,ここまでの説明では,マイナス極からは相変わらず少しの電子しか飛び出していないことになる.これでは電源のマイナス側から導線を伝ってきた大量の電子の行き場がないではないか.回路が途中で詰まってしまう.
そこで,さらにもうひとつの現象を考えないといけない.電子を奪われた気体分子はプラスの電荷を持つことになる.これは「陽イオン」と呼ばれる状態だ.この陽イオンは電場によってマイナス極へ向かって加速されるわけだ.これらの陽イオンはマイナス極の中で待ち構えている電子を受け取って元の状態に戻ることができる.こういう流れも存在しているので,回路全体として多量の電流が流れているように見えるというわけだ.
ところで,電子を奪われた陽イオンが電子を取り戻せる場所は,マイナス電極の表面だけではない.ガラス管の中では大量の電子があるわけだから,わざわざマイナス極まで行かなくても,電子と陽イオンとが再結合を果たす機会は幾らでもあるわけだ.電子が陽イオンに取り込まれて,元の安定な電子軌道へと戻るときに,余ったエネルギーは光として放たれる.ガラス管の内部が広い範囲で光を放つのはこういうわけである.いや,これだけでは説明不足だ.これ以外にも光が出る仕組みがある.
加速された電子との衝突によって,いつも必ず分子内の電子が剥ぎ取られるとは限らない.分子内にある電子が衝突で幾分かのエネルギーをもらうだけで,剥ぎ取られるのを免れることだってある.実はこういう場合の方がはるかに多いかも知れない.気体の密度にもよるが,十分に加速された電子だけでなく,十分に加速されないで衝突する電子も一杯あるだろうからだ.分子の中には電子の軌道が幾つもあって,エネルギーの高い軌道へと移動するというわけだ.これを「励起」と呼ぶ.この用語は「電子が励起される」とか「分子が励起される」とかいう具合に使われるが,主語は違っても意味は同じである.そういう励起されて高いエネルギーの軌道にある電子が元の軌道に自然に落ちる時にも余った光を出す.
これでガラス管内が光る理屈も,真空放電に高電圧が必要な理由も理解できただろう.しかし以上の説明はかなり大雑把なものである.現実には気体の密度や電圧のかけ方によってガラス管の中にできる光の模様が色々と違ってくる.それは加速のされ方や衝突の頻度,再結合の起こる場所などに違いがあるからだ.こういうことを細かく踏み込んでいくと結構複雑であり,現在でも「プラズマ物理」のような形でさらに深い研究が続いている.
さて,光り方が色々と違っていても,その光をプリズムで分解した時に観察できるパターンというのは管内に封入した気体の種類によって決まっており,気体の密度や電圧の影響はあまり見られない.(ある部分が見えにくくなったりとか,そういうことはあるけれども.)これは気体の分子内,原子内の電子の軌道のエネルギーの差を観察していることになるからである.
電子の発見
ここまでの説明は,電子の存在や原子の構造を知った上でのものであった.しかし電子という粒子の存在が確認されて認められたのは 1897 年のことである.20 世紀の直前まで,このような話は全て謎のままだったわけだ.なんとまぁ,考えてみればまだ 100 年ちょっと前,つい最近のことではないか.一体どんな実験が電子の存在を確実なものにしたのだろう.
陰極線は薄い紙のようなものなら透過することから,その正体は波動ではないかという説があった.一方,磁場によって進路が曲がることから,電荷を持った粒子がローレンツ力を受けて運動しているのだろうという粒子説もあった.ところが粒子説に不利な事実もあった.電荷を持った粒子であるならばその進路の途中に静電場をかけてやれば曲がるはずだが,なぜかほとんど曲がることがなかったのである.
え?この話はちょっとおかしいのではないだろうか.陰極線の進路の途中に電場をかけてやれば簡単に進路が曲げられることは現代では常識だろう.高校の物理でも,もしちょっと熱心な教師に恵まれれば,授業中にでも示してくれるような簡単な実験である.テストにも出る.陰極線を曲げるために必要な電圧は数ボルトあるいは数十ボルト程度で良かったはずだし,オシロスコープもこの原理で動作している.
テレビのブラウン管の場合は磁場で電子の進路を曲げている方式がほとんどだからちょっと違う.静電場による制御では広い範囲をカバーするのには不利なのだそうだ.
当時,静電場によって陰極線を曲げることができなかった原因は今でははっきりしている.それは到達できる真空の度合いがまだ十分ではなかったからである.現在の真空管やブラウン管の内部の気圧は 10 億分の 1 気圧程度であるが,当時はまだ 1 万分の 1 気圧か,せいぜい頑張っても 10 万分の 1 気圧くらいのレベルなのであった.
真空度の違いで何が変わるのだろう.上の方で話したように,気体の分子が多くあると,加速された電子は気体分子に衝突して陽イオンを作り出す.その時に散乱された電子と陽イオンとが,偏向用の電極の方へ集まってしまって,静電場を打ち消してしまうのである.
1897 年,J.J.トムソンは苦労して真空の度合いを上げることで,陰極線が確かに電場によっても曲げられることを示すのに成功したのだった.こうして陰極線の正体が,ある一定の電荷と質量を持つ粒子の集まりだと考えても矛盾がないということになった.この実験によって,電子の電荷と質量
の比である「比電荷」
を求めることができる.それは,陰極線が磁場によって曲げられる度合いと比較しても矛盾のない値であった.
電子の質量を導くためには電子が持つ電荷の値を知る必要がある.それが正確に求められるのは 1909 年のことなのでもう少し後のことではあるが,電気分解の実験や化学の分野の知識から,最小の電荷量というものが存在するだろうという予測はすでにあったようだ.それで,今ではこの 1897 年が電子の発見の年である,ということになっている.
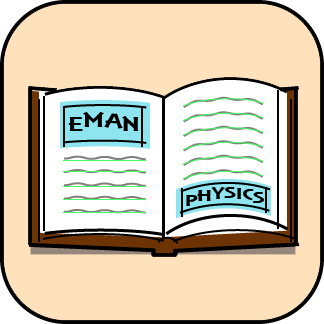










本質的にはこの頃の実験と変わらない。