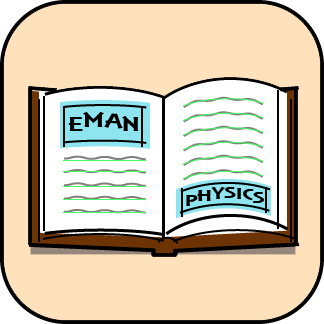ハーバー・ボッシュ法
やっと20世紀に入った!最初に挙げたい大事件は,1906年に開発された「ハーバー・ボッシュ法」である.これによってアンモニアの大量生産が可能になった.
アンモニアは窒素と水素から出来ている.地球の大気の約80%は窒素であるが,残念なことに分子の結合が強すぎてほとんど反応してくれない.これを一旦アンモニアに変えてしまえば,そこから色んな反応を起こせるようになるのである.
これは高温,高圧に耐えられる鉄の容器を作る技術によって可能になった.また,反応を促進する触媒の開発も重要であった.
それ以前は天然の硝石の採取に頼るしかなかった.硝石とは(硝酸カリウム)である.天然の硝石は主に生物によって作られる.人や動物の糞尿に含まれるアンモニアを硝酸菌が分解することで生じるのだ.しかし水によく溶けるので雨が降るところでは流れていってしまうし,植物が肥料としてすぐに吸収してしまうので条件は厳しい.雨が入らないところにある古井戸の壁や,古民家の床下の土から採取された.水によく溶けるのは悪いことばかりでもない.これらの土を水に溶かして上澄みを取って煮詰めれば純粋な結晶が取り出せる.
人工的に硝石を作るための小屋も作られた.雨が入り込まないように屋根を付けて,糞尿をまいておくわけである.
なぜそこまでして硝石を作ったかと言えば,硝石は黒色火薬の原料だからである.硝石自体は危なくはないのだが,木炭や硫黄と混ぜて点火すれば爆発的に反応する.
19世紀の幾多の大規模戦争での火薬需要を満たすためにはそのような生産では全く足りず,南米チリの砂漠から「チリ硝石」が大量に輸入された.これは硝酸カリウムではなく,硝酸ナトリウムであるが,性質は似たようなものである.同じように使えるし,必要なら硝酸カリウムに作り直すこともできる.なぜそんなところに硝石の鉱山が形成されていたのか.以前は海藻を食べた海鳥の糞が集まったものではないかと推測されていたようだが,本当のところは現在も不明なようである.
ハーバーボッシュ法によって社会にどんな変化が起きたかはここまでの話から容易に想像が付くだろう.
肥料が安く作れるようになったのだ.動物や人間の糞に頼らなくても良くなった.化学肥料の使用によって人間に寄生する寄生虫の生活環を断つことに成功した.自然界に窒素化合物が大量に行き渡るようになり,植物はよく育つようになり,食物の生産が増えた.飢饉が減り,世界人口が急激に増加した.現代人の体の半分以上の窒素はハーバー・ボッシュ法により生み出されたものだと言われている.
もう一つの側面は,戦争のコストが下がったことだ.火薬を幾らでも作り出せるようになった.当時,「ドイツでは空気から爆薬を作り出す技術が開発されたらしい!」と恐れられたのだった.
こうして,化学の教科書によく出てくる工業技術,「ルブラン法」「ソルヴェイ法」「ハーバーボッシュ法」を紹介し終えた.なぜそんな古臭いものを学ばなければならないのだと思ったものだ.人類が文明を失ってしまって1から再建する必要が出てきたときには,ロードマップとしてとりあえずこれらの技術の復活を目指してほしいと思う.
原子の構造
次の大事件は原子核の発見である.
ラザフォードが弟子たちの技術の腕を鍛えるためにやらせていた実験によって偶然に発見された.金箔にアルファ線をぶつけたときの僅かな方向の散らばり具合を丁寧に調べていたのだが,ごく少数のアルファ線だけが信じられない角度で跳ね飛ばされていることが分かったのだ.これは「ガイガー・マースデンの実験」と呼ばれており,あまりにも不思議な現象だったため,1908年頃から1910年頃まで改良を重ねて行われた.
1911年になってラザフォードがその実験結果を正確に説明できる理論を作り上げた.原子の中心に高密度の塊,つまり,原子核があることが結論されたのである.
ラザフォードが理論化に成功したことから,この現象は「ラザフォード散乱の実験」などと呼ばれることが多い.しかしラザフォード自身は実験していないのでちょっと気を遣う.
このような実験が行われた背景を知るためには少しだけ時代をさかのぼる必要がある.19世紀の終わり頃には放電実験が流行り,その光をプリズムで分解することで,原子の内部のエネルギーを分析することが行われてきた.「分光学」と呼ばれるものである.当時はまだ原子が実在することを認める人は多くなかったが,エネルギー的な構造については詳しく理解し始めていたのである.
蛍光についての研究もその頃から進んできていた.またそのような研究から派生して放射線やエックス線や陰極線が次々と発見されたし,電子が粒であることも分かって来ていた.「ガイガー・マースデンの実験」もそのような新しい道具を使った地道な研究の一つだったのである.
しかし,それにしても,原子が具体的にそんな構造をしていようとは!電子が原子核に墜落してしまわない理由は量子力学の誕生まで理解できない謎となった.
分子の構造
原子の構造が発見されたのとほとんど同じ時期,1912年あたり,化学にとって強い武器になる大きな技術的進歩があった.「エックス線による分子構造の解析法」である.
化学物質の結晶試料にエックス線を当てたときに特定の方向にだけ強く反射が起きる.これを写真に撮ると格子状に配置された光の点が映るわけだが,それをラウエ斑点と呼ぶ.これを数学的に解析することで,結晶内の原子の並びの幅や角度が特定できるのである.
この技術により,ある程度の大きさの結晶をうまく作ることができれば,その構造を分析,把握することが可能になったのである.
量子力学の誕生
原子核の周りを電子が回っているような構造でなぜ原子が壊れてしまわないのかと物理学者たちが議論を続けた.やがてド・ブロイによる物質波の思いつきをきっかけにシュレーディンガーが方程式を作り,1923年に量子力学が生まれた.そこから数年の熱い議論により量子力学の基礎がほぼ完成する.
量子力学の内容がほぼ問題ないということが分かってくると,それを応用して身近な現象を説明しようという動きが出てくる.ここで物理学者たちがどんな問題に取り組んだのかを列挙したいところだが,すぐに化学の問題に手を出さなかった言い訳のようになってしまうのでやめておこう.実際には化学の問題への応用もすぐに始まるのである.
応用以外への問題でも忙しかった.原子核の中にある陽子を結びつけている力は何なのかとか,陽子と電子だけでは原子核のスピンが理論と合わないからどうしようかとか.ちなみに中性子が発見されるのは1932年である.原子量や原子番号の正体を正しく理解するのにもう少し時間が必要だった.
1926年には「電子線回折による分子構造解析」が可能になる.電子も波であることが分かったことからの成果である.理論的にはエックス線による解析と似ているが,電場の影響を受けて曲がるので,他の情報を得ることもできるようになった.
さらに似た技術なのでここでついでに話してしまうが,1945年には「中性子回折による結晶構造の解析」も使えるようになった.中性子は磁気モーメントを持つことから,この方法では磁気構造の情報を得ることもできる.
電子と原子の世界観
量子力学が発展していく中で,化学者たちも静かにしていたわけではない.並行する形で,原子や電子の存在を前提とした世界観での理論の再構築が進んでいた.少し時代を巻き戻して一気に話してしまおう.
1884年にアーレニウスは水溶液の酸性や塩基性を次のように定義した.水に溶けたときに水素イオンを生じる物質が酸性で,水酸化物イオン
を生じる物質が塩基性であるというものである.中学校の理科では今でもそのように教えられている.
1916年に,ルイスは電子を点で表した図を使って分子結合を説明する方法を提案した.そのような説明図は「ルイス構造式」と呼ばれている.原子の周りに8個の電子を共有することで安定するという考えは「オクテット則」と呼ばれている.量子力学によって電子軌道が説明される以前の経験則ではあるが,本質を突いていると思う.
1923年に,ブレンステッドとローリーはそれぞれ独立に酸と塩基の理論を発表して,アーレニウスによる定義をバージョンアップさせた.水素イオン,陽子,プロトン,どんな表現をしても同じものを意味しているわけだが,とにかくを受け渡す側が酸であり,それを受け取る側が塩基である,とした.これによって水溶液中の反応以外でも酸や塩基を定義できるようになった.何が酸で何が塩基であるかは,反応によって違ってくることになる.高校の化学で習う酸と塩基の定義はこれである.
さらに同年,先ほども出てきたルイスも,酸と塩基の別の定義を生み出している.分子の結合に使う電子対をもらう方が酸で,提供する方が塩基だと決めるのである.いかにもオクテット則を考え出したルイスらしい定義である.は電子が無い状態だから,いつも結合に際して電子をもらう側であり,こう決めておけば従来の定義を崩さないで済む.それどころか,水素原子が含まれていないような反応であっても酸と塩基を定義できるようになったのである.これは大学で習う酸と塩基の定義である.
アルカリ性と塩基性はほぼ同じ意味である.どちらもアーレニウス以前,もっとずっと古くからある言葉である.専門家たちの多くは「塩基性」という用語に統一したいようである.しかし小中学校では「アルカリ性」という言葉を教えているし,世間にも普及しすぎているので,「水に溶けたときに塩基性を示す物質をアルカリ性と呼んでも許すことにする」という感じに制限して,仕方なく認めている雰囲気がある.
ここからしばらく進んで,1938年,ラティマーにより「酸化数」という概念が定義される.それまで,酸化といえば酸素と結びつくこと,還元といえば酸素が外れることであった.しかしそれを拡張して,酸化とは電子を失うこと,還元とは電子を得ることだと考え直したのである.こうして,酸素が含まれるかどうかに関係なく化学変化を理論的に扱うことができるようになった.
それまでの地球人の化学理論は,水や酸素が豊富にある環境を前提としたひどく偏ったものだった.しかし今や,異なる環境に生まれた宇宙人に見せてもおそらく問題ないだろう形式に生まれ変わったのである!
そして現代へ
1930年代から1940年代にかけて,ポーリングが量子力学を使って化学結合の原因や性質を次々と説明していった.こうして「量子化学」が始まった.教科書にも出てくる「混成軌道」や「電気陰性度」などは彼の研究によるものである.
同じ頃,「分子生物学」という分野も生まれる.分子構造の解析技術や化学現象の物理的な理解が進んだので,そろそろ生物学についても,物理や化学の視点であれこれ説明できるのではないかという機運が高まったのである.この頃になって,物理学者の多くが活躍の場を求めて化学分野へと転向していった.
1953年にはワトソンとクリックによるDNA分子の二重螺旋構造が解明されていよいよ盛り上がる.生物学と化学の境界はだんだんと薄れていった.この辺りからノーベル化学賞とノーベル生理学医学賞の受賞内容が入れ替わったかのような状況が増えてくる.
「分子生物学」の他に「生化学」という分野もある.これらの分野名は現在ではあまり区別なく使われたりもするが,生化学の源流は19世紀の有機化学あたりにある.分子生物学の方は,DNA構造の解析などに関心を持って集まった人が多いので,現在でもタンパク質や酵素の構造解析に集中している傾向がある.一方,生化学の方は比較的小さな分子の働きを研究しているイメージである.
さらに「計算化学」と呼ばれる分野も誕生する.量子力学を現実の問題に応用するためにはもちろん計算しなければならない.しかしそれは簡単なことではなかった.物理学者は何とかして計算を楽にするための手法を幾つも生み出したが,それでも忍耐力の要る手計算が必要だった.
1940年代になると大型コンピュータが開発され,やがて第二次世界大戦が終わると軍事以外の科学計算にも使えるようになった.詳しく書くとコンピュータ史になってしまいそうだからほどほどにしておこう.コンピュータの性能が上がるにつれて,複雑な化学結合の計算もできるのではないかという希望が見えてきた.
目的に応じて様々な計算手法が開発され,弱点を克服するための改良が続けられた.どの手法がいつ頃に使い始められたかを言うのはなかなか難しい.初めに理論的に提案された時期と,それを使って計算できるほどまでにコンピュータの性能が追い付いた時期と,実用的な問題にまで使えるようになって流行り始めた時期がそれぞれ数十年ほど離れていたりするからだ.
1990年代には簡単な分子についてなら家庭用のパソコンでも計算できるようになってきた.それ以後もコンピュータの性能の進歩は少しも止まらずに続いている.どの手法も計算の負担を大幅に抑えるために実際の実験から得られた値を使ったりして多少のずるをしているものだが,最近では一切の仮定を置かずに量子力学の原理だけから全てをコンピュータ上に再現できる可能性も見えてきた.必ずしもそこまでする必要はないのだろうが,出来たら出来たでさらにその先が見えてくるのだろう.