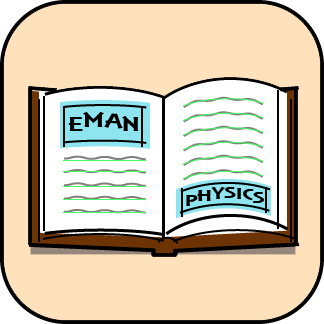これまでのあらすじ
「S行列の物理的解釈をする前に確率振幅がどんな形で求められるのかを説明しよう」などと言ってから随分と時間が経った.結局,まともに結果が出たのはスカラー場の 1 次の摂動だけであって,2 次の摂動では結果が発散してしまったのだった.そしてそれを解決する方法(くりこみ理論)を説明しようとするとさらに話が長くなりそうだというのだ.
あらゆる状況についての確率振幅が求められるようになるまで,このまま苦しい修行を続けてもいいのだが,それを求めることに一体どんな意味があるのかを知らないままというのはあまりにつらすぎる.おおよその雰囲気だけは分かってきたと思うので,話がこれ以上複雑になる前に物理的解釈の話をしておく方がいいだろう.
衝突断面積の定義
まずは衝突の断面積について簡単に復習することから始めよう.以前に「ラザフォード散乱」という記事で衝突の断面積について説明したことがあるが,その最初の方とほとんど同じ話を今から繰り返すことになる.少しだけ急ぎ足で説明するので,もし分かりにくければ以前の説明を参考にしてほしい.今のところ,ラザフォード散乱の説明を最後の方まできちんと理解している必要はない.
古典的な粒子の衝突をイメージしてほしい.標的粒子が並ぶところにほとんど大きさ 0 の弾丸をランダムに撃ち込んだとき,標的にぶつかるかどうかの確率は標的の断面積の大きさで決まるのだった.
多数の弾丸粒子は一定速度で筒状の領域内を進んでくるものとする.その筒状領域の断面積を
としよう.
一方,標的粒子の数は個で,どれも弾丸粒子側からは重なって見えないほどにまばらに配置されているものとする.標的粒子 1 個あたりの断面積を
とすると,標的の合計の断面積は
であり,それが断面積
のコースの幾分かの面積を塞いでいることになるわけだから,そこを進む弾丸粒子が標的粒子に当たる確率は
と表される.
さて,この確率と弾丸粒子の個数とを掛け合わせれば衝突が起きる回数を知ることが出来るであろう.弾丸粒子群は
秒間に
だけの距離を進むのだから,
秒間に
という体積内にある弾丸粒子が全て次々と標的粒子群の中に突っ込むことになる.弾丸粒子群の密度を
とすれば,この体積内にある粒子の数は
と表せる.
これで弾丸粒子の数と当たる確率が分かった.秒間に衝突が起こる回数
は次のように表すことが出来る.
この式では標的粒子の数を
として表しているが,こちらも標的粒子の密度
を使った形で表しておきたい.なぜなら,粒子群どうしを正面衝突させる場合,どちらが弾丸粒子でどちらが標的粒子であるかの違いはないからである.両者を対等なものとして扱うような式にしてやりたい.
標的粒子が配置されている領域の厚みをとすると,体積
の中に
個の粒子があることになるので,
と表せる.つまり
である.これを (1) 式に放り込んでやると次のようになる.
さて,ここまではイメージしやすくするために衝突が起こる場所を円筒領域内に限ったり,標的粒子群の厚み
というものを設定したりしたわけだが,そのような制限を取り払って考えよう.粒子密度がそれぞれ
,
であるような粒子群どうしが相対速度
で接近し,そのまま同じ領域内をすれ違い続ける限り,領域内のどこであっても均等に同じ状況が起こり続ける.加速器の中で起きる衝突のイメージに縛られる必要はない.例えば,宇宙全体で大規模にこのような衝突が長時間起き続けている様子を想像してもいい.(2) 式の
の部分を体積
に書き換えてやると次のようになる.
これが,
秒間に体積
内で起こる衝突の回数
を表す式である.
さて,この (3) 式を眺めていると,まだ不満がある.ここまでは標的粒子のみが有限の大きさの断面積を持ち,弾丸粒子の方は大きさのない点として考えてきたわけだが,それだと両者が対等だとは言えない.では,どちらも有限の大きさを持つ場合にはどうなるのだろうか.どちらも球体である場合には両方の断面積の和を
として使えばいいことが示せるが,それ以外の場合には良く分からない.複雑な形どうしの物体が不規則なぶつかり方をするので単純な法則としては表せなくなるだろう.
素粒子の反応を考えるときの断面積はもっと分からない.素粒子ははっきりと決まった大きさのある存在ではないし,反応の起こりやすさは粒子のエネルギーなどによっても変化する.だから (3) 式を並べ替えて,
のように表し,これを素粒子反応の断面積であると定義することにする.つまり,粒子密度がそれぞれ
,
であるような粒子群どうしが相対速度
で同じ空間をすれ違い続けている間に,その中のある部分の体積
の中で
秒間に
回の反応が起きるとき,その反応の断面積の大きさを
だと決めるのである.反応の起こりやすさの指標として,形ある物体同士の衝突の断面積の考え方をそのまま利用しようというわけである.
衝突した粒子のどちらがどの程度の断面積を持っているかということはもはや少しも考えず,「反応自体の断面積」というものがあると考えることにする.反応の種類ごとにそれぞれ違った断面積があるということである.
微分反応断面積
ところが素粒子の反応というのは実に微妙であり,衝突が起きたか起きなかったかというような二択で分類できるようなものではない.
ラザフォード散乱を思い出してもらうと良いのだが,粒子の進路がごく浅く曲げられるのも強く曲げられるのも,どちらも衝突の一種であると考えられる.さらに,限りなく僅かだけ進路が曲げられた場合と全く曲げられずに素通りした場合との明確な境目さえもないと来ている.
しかし反応によって別種の粒子へと変化してしまう場合にはどうだろうか?これについては衝突が起きたかどうかははっきり判断できる.それでもその粒子がどの方向にどれくらいの運動量で飛び出していくかというところまで考えると様々な状況があり得る.
粒子の種類が変化してしまう場合もしない場合も衝突の一種だと考えられるので,「どんな粒子がどんな運動量を持って出ていくか」を指定して,そのような結果を起こすような衝突の確率というものを考えることにしよう.運動量というのは 3 成分あるので,今言った「どんな運動量を持って出ていくか」という表現は「どの方向にどんなエネルギーを持って出ていくか」という意味でもある.
例えば次のような反応を想定してみよう.
粒子
,
,
,
の運動量をそれぞれ
,
,
,
と表すことにしよう.これは今までの計算で使ってきた記号に合わせてみたのである.しかし今までやってきた
4乗理論の計算では
,
,
,
はどれも同じ種類の粒子であるような反応しか表していないのだった.もし
と
が異なる粒子であるなら,どちらか一方の種類の粒子のみを検出する装置を使って衝突反応で出てくる粒子を測定してやって,1 個の粒子が観測されるたびに 1 回の衝突が起きたとカウントしてやればいい.しかし
と
が同種粒子の場合には 1 個の粒子を検出しただけで 1 回の衝突が起きたのだと考えてしまうと数えすぎになってしまう.出てきた 2 つの粒子をペアにして 1 回の衝突が起きたとカウントしてやる必要がある.
検出器の仕組みや分析方法にまで踏み込むと話がややこしくなるので,「実際にはそういうところまで考慮しなければならないのだ」という注意喚起にとどめておこう.詳しくは後回しだ.
粒子と
の運動量がそれぞれ,
,
という微小範囲に入る形で出てくるような衝突が起きた回数を
と表すことにしよう.このとき,(4) 式をそのまま使って,次のように表すことが出来る.
この
のことを「微分反応断面積」と呼ぶ.粒子の種類が変わらない場合には「微分散乱断面積」と呼ぶが,理論上はあまり違いはない.
なぜこれを「微分」断面積と呼ぶのだろうか?というのはただの反応の回数を表していて特に微分と関係ありそうにもない.ところが軽く聞いた限りでは見落としてしまうことがある.
と
という範囲を指定している部分が無限小なので,
というのも実は無限小なのである.おそらく (5) 式はこのあとであれこれ変形していくと
のような形に表されるようになるはずであり,これを次のように積分することで「全反応断面積」
が得られるようになるはずである.
特に,粒子の種類が変わるような反応について「全反応断面積」を計算すると,「変化後の粒子がどの方向へどんな勢いで飛び出して行ったか」という分布についての情報は消えてしまうが,「とにかく粒子の種類が変化する確率は全部でどれくらいあるのか?」というのを表す量として使えることになる.
散乱と反応の違い
もう気付いていると思うが,場の理論で「粒子間に力が働いて運動量が変化して飛び出してくる」というのは,元々あった粒子が消滅演算子によって消されて,それとは異なる運動量を持った「元と同種の粒子」が生成演算子によって代わりに生まれてくるという形で記述されている.元々あった粒子に力が働いて連続的にぐねぐねーーーっと方向を変えたというようなイメージではない.元とは異なる状態へと「一瞬で変化」したのである.
粒子の種類が変わって出てくるのはそれと全く同じ仕組みであり,相互作用の形が複数の種類の場の組み合わせになっているというだけの違いでこのようなことになる.異なる種類の粒子が存在するような状態へと「一瞬で変化」しただけなのだ.
一般向けの解説で今でもよく見かける「光子のキャッチボール」みたいなことは実際には起きていない.あれは本当に牧歌的なたとえ話だと思うし,理解を妨げる原因にもなっていると思う.
その変化は観測によってもたらされたと言えるかもしれない.観測していなくても勝手に起きる現象なのではないかという見方も出来るが,飛び出してきた粒子を観測したことによって初めてその状態へと定まったのだと見ることも出来る.素粒子の反応というのも,量子力学的な観測の理論の延長上にあるのである.
素粒子反応で飛び出してきた粒子を観測するまでは,起こり得るあらゆる反応の結果が重なって存在している……だと!?
今すごく大事なことを言ったので,今回の記事はここで一旦終わりにしようかとすら思った.しかしまだ本題に入れてもいないので,続けざるを得ない.
確率振幅との関係
この (5) 式を実用的に使えるものにするためにはの部分を遷移確率と結びつけて置き換えてやる必要がある.これまで計算してきたのはS行列の複素振幅であって,その絶対値の 2 乗が確率を表している.今のところ,1 次の摂動しかうまく求めることができなくて,それは次のような結果となったのだった.
実はまだ説明していなかったのだが,何次の摂動であってもこれと似たような形として結果が得られるのである.精密な結果を得ようと思えば,1 次の摂動だけでなく,2 次,3 次,4 次と計算してそれらの合計を使うことになるわけだが,それらの共通部分をまとめて,それ以外の部分を足し合わせたものを
と表すことにすれば,S行列の複素振幅の全体は次のように表すことができる.
この
のことを「不変散乱振幅」と呼ぶ.なぜ「不変」かというと,この部分がローレンツ変換に対して変化しない量であるからである.この解説の流儀では理論形式を隅々までローレンツ不変にすることにこだわっていないので,この部分がローレンツ不変であるかどうかは判断しにくいと思う.ローレンツ不変にこだわった他の流儀と比較してみても,この
の部分だけは同じ形のものが出てくるというわけである.
いや,そこはいいけど,ちょっと待って?というのはエネルギーと運動量の保存則だから何次の摂動を計算しても毎回同じ形のものが出てくるのは分かる.発散してしまった 2 次の摂動からも途中で出てきたのだった.しかし
というのは出てこなかったのではないだろうか?どの摂動項も一緒にしてこの (6) 式のような形にまとめられるというのは本当だろうか?
そこが気になってという因子の出所を探ってみると,どうやら「ファインマン図形の中にループが存在していない限り」という条件で (6) 式のようにまとめられると言えそうである.
というのは各頂点で指数関数からデルタ関数を作るたびに副産物として出てくるのだが,伝搬関数が一つあるごとに
という因子も出てくるのでこれらが互いに打ち消し合ってしまう.頂点の数と,それらをつなぐ内線の数を比較してやると,ループが存在していなければ必ず一つだけ
が余るはずなのである.くりこみ理論というのはループを消すような処方らしいので,それを適用するところまで考えれば (6) 式のような形になると言ってもいいのだろう.
さて,(6) 式は確率振幅であるから,確率密度を得るためには絶対値の 2 乗を計算する必要があって,次のようになる.
デルタ関数の 2 乗というものが出てきてしまってどう扱ったらいいかと迷うわけだが,デルタ関数というのは「やがて積分されなければならないもの」であるから,同じものが 2 つあるからといって一方を勝手に消してしまうわけにはいかない.今すぐ積分する理由はないのだが,いつか一方のデルタ関数だけに注目して
か
で積分してやったあとにはもう一方のデルタ関数の中身が 0 に変わったものが残るだろうというので,ここではちょっと先走って
と書いてある.
数学的にはデルタ関数の 2 乗というものはうまく定義されていないのだが,ここでは極めて物理学的に,大雑把な考え方をしているのである.多くの教科書でも,この部分を説明するところでは微妙な気まずさを感じることができて面白いことになっている.
というのは無限大になってしまうのだが,この意味を考えてみよう.デルタ関数の積分表示によると,次のようになる.
要するに,宇宙全体の無限大の体積と,無限の過去から無限の未来までの時間との積である.全時空の体積とでも言おうか,物理的な意味はそんな感じのものである.
そもそも (7) 式が表していたものは,初期状態に対して相互作用が働き続けて無限の時間を経過した後に,指定した終状態に変わっている確率であった.そして初期状態も終状態も,運動量が確定している粒子が幾つあるかという形で表していたのだった.つまり,ここでいう「状態」というのは,宇宙全体までの広がりを持っている粒子を意味しているのであった.すると,(7) 式をで割ったものは,その単位体積,単位時間あたりの遷移確率だと解釈してやっても良さそうである.
今は (5) 式の
に相当するものを探しているつもりだったのだが,この調子で行くと,どうやら
に相当するものを得ることになりそうである.(8) 式は 1 個の粒子
,1 個の粒子
を仮定して一つの反応が起きる確率を表しているので,これに初期状態の粒子の数を掛けてやれば,単位体積,単位時間あたりに反応が起きる回数を表す式にできそうである.
ところで,初期状態の粒子の数というのは実際の実験では何に該当するのだろうか?や
がそれに当てはまりそうだが,これらをただ掛けてやればいいのだろうか?いや,何かおかしい.これらは「粒子密度」であったから,宇宙全体での個数を考えると無限大になってしまうではないか!どう解釈してどう当てはめてやればいいというのだろうか?
状態の解釈
正しい推論が出来ているかが心配になってきた.ちょっと状況を確かめてみたい.これまではずっと,初期状態として 2 個の粒子があるような状況を考えてきたが,とりあえず基本に立ち返って 1 個だけある状態について考えてみよう.
この意味を探るために,別の運動量
の粒子がある状態を考えて,それとの内積を取ってみよう.
まぁ,特に気になることもないシンプルな結果である.ここで
の場合を考えると,
のようになって,ここにもまた無限大が出てくる.この無限大も先ほどのように物理的な解釈をしてやると,
のようになり,この体積
が宇宙全体の無限大の体積を意味している.なぜこんなにも理論のあちこちに無限大が出てきてしまうのか.それともこじつけ的な解釈であって,これ自体に意味はないのだろうか.
さらに探ろう.は
の完全性を利用して次のように変形できる.
つまり,1 粒子だけが存在する状態
というのを座標表示してやったものは量子力学の波動関数と同じものなのだということで,このような見慣れた形に書いてみたのである.最後の行を見ると粒子の存在確率を全空間で積分したものなので 1 に等しいと書いてしまいたくなるのだが,(10) 式では
となっており,矛盾しているように思える.
なぜこんなことが起きているのかと考えてみると,運動量が確定した状態というのは波動関数で表すならであり,一定の振幅がどこまでも続くような形になるのであって,このようなものは有限体積を仮定しないと規格化が出来ないのであった.
これで (10) 式と (12) 式の間に矛盾があるのではないかという疑いは晴れたが,全宇宙に粒子が 1 個だけあるという解釈についてはうまく定義が出来ずに怪しくなってきた.もし有限体積内の場の理論として話を進めていればこのような問題は避けられたはずである.ただし,その場合には運動量は離散的になり,積分の代わりに和の記号ばかりが出てくる流儀になっていただろう.
この話をするときだけ急に有限体積内の場の理論の流儀になる教科書もあったりして,話を追いきれずに混乱させられたりもする.
では体積が無限大の中で起こる,連続な運動量についての場の理論はどう進めていけばいいのだろうか.(12) 式が粒子の個数を表すのだという解釈は足掛かりとして頼りになりそうである.そうすると,(11) 式にあるように,宇宙全体では個の粒子があるのだという解釈を採用することになる.これを体積で割ってやれば個数密度になる.つまり,単位体積あたり
個だということである.
これまで (9) 式を「真空中に 1 個の粒子がある状態」と言ってきたわけだが,実は「真空中に運動量の粒子が個数密度
で一様に存在している状態」を表していると考えるべきだったのである.これは今の流儀ではそう解釈できるという話であって,流儀によって少し違ってくるので注意してほしい.
例えば,ローレンツ不変であることを重視する流儀では,粒子のエネルギーによって粒子密度が違うという形の解釈をすることになる.このように,この個数密度というのは単に流儀によってそう解釈せざるを得ないというくらいの違いであるから,特に物理的に重要な意味はないのである.
少し補正して完成
(8) 式は 1 粒子どうしの反応確率を表すのだと思っていたが,どうやら個数密度がである粒子どうしの反応確率のようである.反応確率はそれぞれの粒子の個数密度に比例するのだから,個数密度が 1 の粒子どうしの反応確率にするには (8) 式に
を掛けてやる必要がある.
この式の元になった (7) 式は確率密度だから,微小確率を得るためには微小幅である
を掛けてやればいいのだろう.初めから掛けておいても良かったのだが,考察の邪魔になるので後回しにしておいたのだった.先ほど調整のために付け加えた
というのは入射粒子の密度に関連しているものなので,入射粒子に関連する係数と相殺する形でまとめておくことにしよう.次のようになる.
これが,粒子密度が 1 の粒子どうしを衝突させたときに,単位体積,単位時間あたりに反応が起きて
の範囲へ飛び去る確率である.単位体積内に 1 個と 1 個の粒子があるだけなので,それはそのまま,単位体積内で単位時間に反応が起きる回数として解釈できるだろう.この状況を (5) 式に当てはめれば,
,
,
,
なので,
という公式が得られることになる.目立たないが,分母に粒子どうしの相対速度
が入っていることを見逃さないようにしよう.